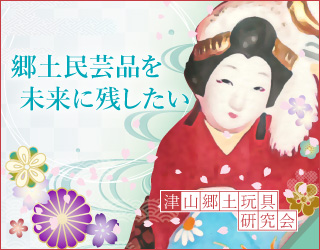雛人形 通販|ネット予約・注文2026|専門店・百貨店・総合通販サイト|木目込飾り・衣裳着
鶴岡雛菓子

鶴岡雛菓子のおひな菓子は、山形県鶴岡市の「木村屋」や「藤田菓子補」「住吉屋菓子舗」などで作られています。
上生菓子で作られたタイやエビ、サクラマスの切り身、庄内柿、孟宗竹、さくらんぽなどがひな飾りの前に添えられるのが、鶴岡雛菓子です。
藤田菓子補 おひな菓子 1セット
4,100円 送料無料
- 個性が光る「ねこ」も入っている藤田菓子補のおひな菓子は、「タイ」や、山形の特産品「さくらんぽ」などを模した上生菓子入りです。
- 中でも面白いのが「マスの切り身」。こんがりとした焼き目までリアルに表現されています♪
- 練りきりでナスやアケビも作り、できた菓子に溶かした寒天をハケで塗って照りを出しています。
江戸時代からの伝統和菓子
「鶴岡雛菓子」の始まりは江戸時代に北前船の寄港地の一つでもあるのが庄内藩の城下町である鶴岡でした。

上方の文化と参勤交代でもたらされた江戸の文化が融合し、独自の食文化が創始されたといわれています。
1800年代には城下の菓子店におけるひな菓子のランク付けがされていました。
その時代の客の好みに合わせつつ、職人たちが独自性を追求してきた技の最終段階が「鶴岡雛菓子」なのです。
かつては、「菊一」呼ばれる打ち物(落雁)の上に、同じ打ち物のお多福やタイ、ゼンマイ、タケノコ、アメ細工でできたキノコなどが置かれた盛り菓子スタイルが主流でした。

今日では、白あんと*求肥(ぎゅうひ)で作った練りきりです。タイやエビといった縁起物のほかに、地元の特産の温海カブや民田ナス、外内島キュウリなども色鮮やかに再現されています。
*求肥;こねた白玉(しらたま)粉に水あめ・砂糖を加えて練り、蒸して、薄いもちのようにした菓子。
1994年に、全国に例がないひな菓子として報道されて鶴岡雛菓子が注目されました。
200年ほど前には鶴岡市沿岸部でしんこ(白米をひいて粉にし、水でこねて蒸してついたモチのようなもの)の細工をひな壇にあげたという記録があります。
鶴岡雛菓子は旧暦の3月3日ごろまで売られています。
当サイト 人気ひな人形 通販サイト
ひな人形専門店
| 工房天祥 | 秀光人形工房 | 原 孝洲 | 真多呂人形 |
|---|---|---|---|
百貨店(デパート)
| 大丸松坂屋オンラインショッピング | 京王ネットショッピング |
|---|
| 小田急百貨店オンラインショッピング | 三越伊勢丹オンラインストア |
|---|
スーパーマーケット
イオンスタイルオンライン
【老舗通販.net】ひな祭り特集
- 日本の老舗通販.netでは、創業から100年を越える老舗の逸品をご紹介しています。
- お子様やお孫様の健やかな成長を祝うに相応わしい、老舗の逸品を集めました。
LeTAO(ルタオ) ひな祭りケーキ2026
大丸松坂屋のギフト 初節句内祝い
- 初節句に雛飾りや雛飾人形などのお祝いをいただいたら、「ありがとう」のメッセージ入りギフトのお返しがおすすめ!